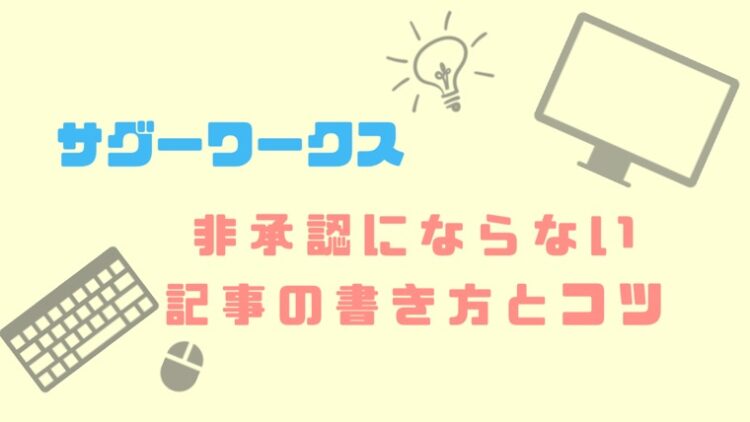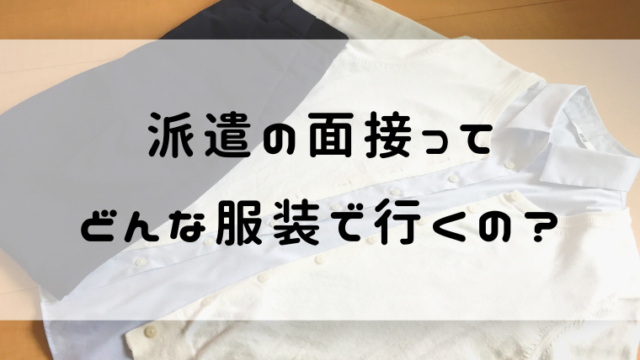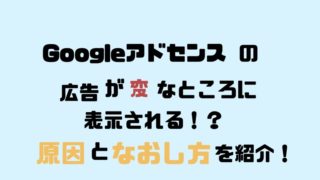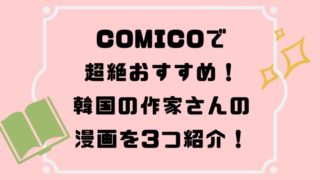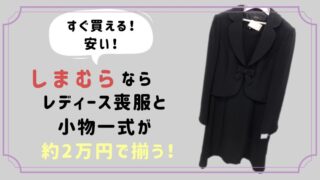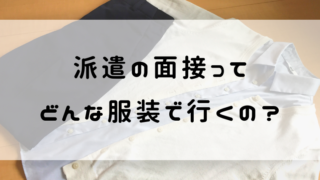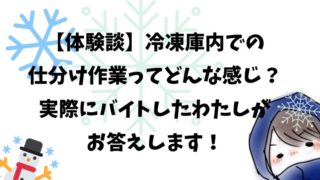サグーワークスで記事作成のお仕事をしていて、記事が非承認になってしまった!という経験はありますか?
もしあるのなら、記事作成のお仕事もやっぱり難しいものだな…とモチベーションが下がってしまう人もいるかもしれません。
けど、コツをつかめば、承認される可能性もぐんと上がると思います!
こんな人におすすめの記事です
- 「指定事項とか気を付けて書いたのに記事が非承認!?なんで!?」
- 「なるべく非承認にならないようにしたいけど、記事を書く時のコツとかないかな?」
この記事を書いているわたし自身、非承認を連続でくらって萎えたので、そのときの経験をもとに承認される記事のコツをまとめてみました。
ライティングの際に役立てていただけると幸いです!
サグーワークスは非承認が多い?

サグーワークスでの記事作成は非承認が多いような気がする…というのは、もちろん人によってそれぞれだと思います。
けれど、わたし自身もサグーワークスで記事作成をやり始めたばかりの頃に、立て続けに3件非承認になったことがあります。
そんな経験から記事作成(ライティング)の初心者は非承認になりやすいのかも、と思います。
一生懸命書いた記事が何度も非承認になると、記事を書く自信がなくなってしまいますよね。
特に初心者であれば、「自分にもやれるかもしれない!」と思って挑戦すると思います。
その結果が非承認の連続だと、「素人にはやっぱり無理なのか…」と、モチベーションを保つのが難しくなってしまいますよね。
わたしも正直3件連続非承認をくらったあと、また非承認になったら「自分には記事作成向いてないのかも」ってあきらめていたかもしれません。
そうならないために記事を書く時に気を付けることやコツをつかもうと、記事を書く前に自分なりに考えて対策をしてからは非承認をくらわなくなりました。
コツや対策など、ちょっとしたことですが紹介していきます。
サグーワークスで記事を書く時のコツ
基本的には以下の項目を熟読することが最重要ポイントです。
- 案件概要
- 指定事項
- ルール
- NG項目
これらは 「記事作成するときに守ってほしいこと」です。
非承認になってしまうのは、これらの項目でお願いされていることを守っていないのが原因なんです。
また、サグーワークスでは記事を納品した後、非承認になったら「アドバイス事項」というところから、なぜ非承認になってしまったのか理由を確認できます。
これは承認された記事も同じで、マイナス点のない記事以外は基本的に「ここを直したよ」という点を教えてもらえます。
そういったことを元にここでは、特に大事だと思ったことや非承認になって気づいたこと、思ったことなどを書いていきます。
どんな人に向けた記事なのかを知る
当たり前と言えばそうなのですが、大事なことです。
案件概要に記載してある、「誰に向けた」「どんな記事」を書いてほしいのかということをしっかり確認しましょう。
特にここで重要なのはこの記事を読むのはどんな人なのかということです。
- 10代~20代の恋愛に悩む女性に向けた記事なのか?
- 釣りが好きな人全般に向けた記事なのか?
- それとも会社のとある部署に向けた記事なのか?
どんな人が読者になるのかはその記事次第ですが、ここを確認しなければ文章を書く方向性が決まりません。
まずはどんな人に向けた記事なのかということを確認しましょう。
文章を書いている人の目線と、それに応じた文章の書き方
指定事項に「目線」という項目がありますが、これがかなり重要なポイントです。
主に第三者目線・客観的目線と主観目線のタイプに分けられると思いますが、これがちょっと難しい。
主観表現は文字通り自分が思ったように自分の目線で書いていいよ、ということです。
レビューや口コミの記事作成には主観表現で書くことを指定されていることが多いですね。
主観表現の場合はブログや日記などでもよく使うであろう、「わたしはこう思う」「使ってみてわたしはこう感じた」という表現がOKです。
一方、第三者目線(客観的目線)と指定されている場合は少し気を付ける点があります。
第三者目線というのは、たとえば新聞や教科書のような文章です。
淡々と物事を語る必要があるので、感情を文字に表すのはNGです。
わたしがよく非承認にされてしまったのは
「〇〇だと思います。」「〇〇のように感じられます。」
という表現。
例えば「一般的に青は清涼感がある色だと思います。」のように書いたとします。
「一般的に」のおかげで客観的な目線になるかと思いきや、やはり「思います」は主観的だからNGとのことでした…。
ちなみに、「青色からは涼しさが感じられます」のような表現もNGです。
そのため、「思います・感じます」とやんわり伝えるのではなく、断定してしまうのが良いのだと気づきます。
「青は清涼感がある色です。」と言い切ると、主観表現がなくなりOKとされていました。
今回は例文で青色を挙げましたが、実際の記事作成では「これってこんなに自信満々に言い切ってしまっていいのかな?」という不安も出てくるかもしれません。
けど、それはあまり気にしなくてよいと思います。あまりにぶっ飛んだこと、一般常識から外れたことでなければ、基本的に文末を断定してしまってOKです。
これを意識するだけでかなり承認率が上がると思います♪
誤字脱字、改行ミスは2か所以上あると非承認率が上がる
わたしの経験上の話ですが、
- 誤字脱字
- 改行のミス
これらは1~2回なら見逃してもらえる可能性が高いです。
個人的には、どの案件も全体的に誤字脱字、改行ミス(〇字を目安に改行してほしいなど)に関しては寛大な傾向にあると思います。
ただ、それに甘えていると1度の誤字脱字などでも非承認になってしまう可能性も考えられます。
アドバイス事項に「次回から非承認になるかもしれないよ」と一言添えてあるので、やはり納品前にしっかりと記事をチェックをすることが大前提です。
同じ文末表現を繰り返さない
指定されている文末表現を使用しているとしても、それが繰り返されていると非承認になってしまう可能性があります。
- 「〇〇しています。」
- 「××します。」
のように、続けて文末が「ます。」となっているとNG…という感じです。
これは、やはり文章がくどくなるというか…言葉に出して読み上げるとどことなく違和感があります。
なるべく文末が同じにならないように文章を作る必要が出てきますね。
誤字脱字ゼロを目指せ!Wordを使って校正する
わたしは今のところ誤字脱字だけが原因で非承認になったことはありません。
でも、無いほうが絶対に良いですよね。
そこでわたしは、PCソフトWordを使って記事を納品前にチェックしています。
Wordでの校正のやり方は以下を参考にしてください。
- Wordを立ち上げ、作成した文章をコピペする。
- 「F7」キーを押すと文章の校正・スペルチェックが始まります。
- 何も修正箇所がなければ、「校正が終了しました」と表示されます。修正箇所があれば、文章や単語のしたに波線が引かれ、「入力ミス?」「ら抜き」など、間違いと思われる点を指摘してくれます。
ちなみに②はタブメニューから校閲→スペルチェックと文章校正からでも同様に校正可能です。
基本的な誤字脱字、ら抜き言葉なども指摘してくれるので、その部分を修正していけば確実性があがります。
Wordでの校正後、最後に自分で読み返してみるのが一番正確だと思いますので、念には念を押して最終チェックもするとなお良いでしょう。
まとめ
記事を納品するとき、失敗したくない、非承認はもうごめんだ、と思ってしまいますよね。
しかし、実際に文章を書いて失敗したり非承認になったり、苦い経験を積むことも大きな経験になると思います。
わたし自身、非承認3連続でくらってだいぶ気を付けて記事を書くようになったので、それも良い経験だったんだなと感じています。
ここでの情報やコツ、他の方のアドバイスなどを参考にしつつ、より良い記事を書いていけるようにしたいですね!